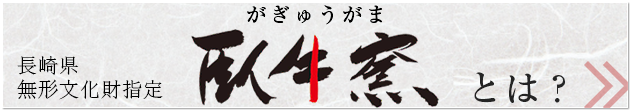お銚子(片口)と徳利の違いについて
お銚子と徳利は似たようなものであり、それぞれにどのような違いがあるのか明確に把握している人は少ないのではないでしょうか。実際にはこれらは異なるものであり、それぞれに用途や特徴があるのです。
お銚子と徳利にはどのような違いがあるのかを見ていきましょう。
■お銚子とは何か
お銚子というのは、お酒を入れて盃に注ぐために使う容器のことです。
本来は金属製ですが、陶器や木製のものもあり、長い柄がついているのが特徴であり、注ぎ口が一つのものが片口であり、二つのものは両口と呼ばれています。
見た目は急須のような形をしていますが、ふた付きのものや、ふたの付いていないものとあるようです。
あらたまった席において使われるのが本来の用途であり、かつては宮廷の祝宴でも使われていました。現在では結婚式の三三九度やお神酒を入れる器として使われています。
居酒屋でお銚子一本と注文して出てくることがあるのですが、あれは本来のお銚子とは別物です。
■徳利とは何か
徳利というのは首の部分が細くて底が太くなっており、ひょうたんのような形をしているお酒を注ぐための容器のことです。
また、徳利の用途はお酒に限定されるわけではなくて、油やしょう油の容器としても使われます。
徳利は日本酒が入っているものは一合から二合程度が一般的なのですが、一升入るような容量の大きなものもあります。
お酒を注ぐ時にはトクトクという音がするものが良いとされています。
それ以外にも、蕎麦屋でそばつゆを徳利に入れているケースも見かけます。
■お銚子と徳利の違いについて
徳利は古くは室町時代からあり、江戸時代になると大量生産により、あっという間に広まりました。
お銚子と徳利は上記のように本来はまったく形の異なるものとなっています。
しかし、居酒屋でお銚子一本と注文してみると、実際には徳利に入った日本酒が運ばれてくることが多いでしょう。
現代においては徳利とお銚子は呼び名が混同されており、本来の違いはほとんど意識されなくなっているのです。 特別な席以外でお銚子が使われることはほとんどありません。
このように徳利とお銚子というのは別のものであり、それぞれ形が全然違います。
しかし、本当の意味でのお銚子を見る機会はほとんどないでしょう。
居酒屋でお銚子を頼んで出てきたものは、本当は徳利なのだということを理解しておきましょう。
ツイート
商品案内
湯呑・碗

窯元ぎゃらりい
佐世保市木原町1897-1
Tel.0956-30-8653
毎週水曜定休日
営業時間 9:00〜17:00